何歳児の保育が向いている? ~年少から年長まで~
何歳児の保育が向いている? ~年少から年長まで~
※注 ここの文章はさまざまな保育施設の一例をまとめたものであくまで目安としてまとめました。実際はそれぞれの子どもの成長にあった保育を行っていきます。
年少組(3~4歳児)※園児20人につき保育士1人必要
生活面では初めの頃はまだおむつをしている子どももいます。しかし身の回りの着替えなど、一人でできる子が日を追うごとに増えていくところが保育者としてやりがいを感じる一つかもしれません。
また、手洗いうがいなども一人でできますがその場で石けんでずっと遊んでいるようなこともよくあるので、目は離さないように心がけることが大切です。はみがきなども一人である程度できますが仕上げなどは保育者が援助します。
4月生まれと早生まれの子の違いは身体の大きさも違ってきます。遊びは砂遊びなどの一人遊びが目立ちますが、保育者が援助することで鬼ごっこなどの簡単なルールの遊びならできるようになります。この頃から先生の手伝いなどしたいという気持ちを持つ子どもも見られ、誰かを呼びに言って連れてくことができたりと言葉を上手に使うことができてきます。
絵本 『ぐりとぐら』 『はらぺこあおむし』
年中(4~5歳児)※園児30人につき保育士1人必要
身の回りのことはたいていできる子が多くなり遊びも年少に比べ活発になっていきます。保育者に依存しなくても子ども同士で活動することもできるようになります。
お遊戯などもだいぶ上手になり、セリフを覚えて行う劇などもできるようになります。お手伝いも簡単なお手伝いはもちろん、先生がいなくても決められた仕事を一人で行ったり、お友達と協力して子どもだけ行うこともできるようになってきます。
絵本 『パンダうさぎコアラ』『ペンギンたんけんたい』
年長(5~6歳児)※園児30人につき保育士1人必要
年長に入ると身の回りの生活習慣(食事、着替え、排泄など)に関して一通りのことができるようになります。
先生の補助を必要とせず、何でも自分でやってみようと気持ちが生まれます。お手伝いなどを積極的に参加したり、いろいろなものに興味や関心をもったり、会話も「な、なんて大人っぽい会話をしているんだ。。」と感じるようなこともあります。
遊びも活発になり、保育者が子どもの体力についていけないこともしばしば。。遊びの内容はたくさんのルールが必要なドッチボール、リレーなどができるようになり、保育者は遊びの援助をして子どもの遊びを楽しく促していきます。
また、保育者の援助の必要とせず、自分たちで遊びを見つけては、工夫して遊んでみたりする姿も見られるようになります。 また楽器などもピアノが弾けたり、太鼓を叩けたり、歌を上手に歌ったりと年少時に比べずいぶん大きな成長を感じられるようになります。
ご両親から離れ、お泊まり保育などを行うことも年長児になってから行うことが多いです。
絵本 『ヘンゼルとグレーテル』

-
おすすめ受講生合格率が通常の3.2倍に!申し込み件数ランキング第1位はあの『〇〇』の保育士講座
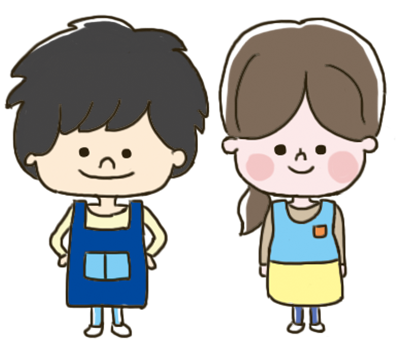
-
広告園見学~勤務中まで保育現場を知り尽くしたあなた専任の人材コンサルタントのサポートが受けられる




